1 特別受益とは
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、それを無視して相続分を決めると、遺贈や贈与を受けていない相続人との間で不公平となることがあります。
そこで、この場合には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その人の相続分は、算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすることとされています。
このような取り扱いをする遺贈ないし贈与を特別受益と言います(903条)。
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+贈与の価額=みなし相続財産
特別受益者の相続分=みなし相続財産×その人の相続分割合-遺贈又は贈与の価額
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。
2 特別受益者の範囲
相続人に限られます
(1)判断時
特別受益の持戻しをする必要があるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者に限られます。
そして、特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
(2)被代襲者に対する生前贈与等
被代襲者は、生前贈与等を得た時点では、推定相続人です。
代襲者は、そのような被代襲者の地位を代襲して取得するだけであって、被代襲者以上の相続による利益を取得することはできません。
したがって、被代襲者に対する生前贈与等は、代襲相続人の特別受益として算入すべきことになります。
(3)代襲者に対する生前贈与
代襲原因発生前に贈与等がなされても、その時点では代襲者は推定相続人ではありません。したがって、その生前贈与は、他の第三者に対する贈与と同様の性質であるため、特別受益には含めないことになります。
一方、代襲原因発生後に贈与等がなされた場合、その贈与等を受けた代襲者は、その贈与等を受けた時点で、推定相続人となっているため、生前贈与等は特別受益に該当するとされています。
(4)推定相続人となる前の生前贈与等
例えば、養子縁組前に養子となるべき者に与えた金銭、婚姻前に妻となるべき者に与えた金銭などが挙げられます。
原則としては、推定相続人となる前の贈与は特別受益に該当しませんが、贈与が養子縁組 (婚姻) をするために、又は養子縁組 (婚姻) することが調ったことによりなされた場合等、推定相続人となった後の贈与と実質的に同視できる場合には、特別受益に該当します。
(5)相続人の配偶者その他の親族に対する生前贈与等
特別受益の持戻しの対象となるのは、相続人に対する贈与に限られます。
したがって、相続人の親族に対して贈与があったことにより相続人が間接的に利益を得ていたとしても、相続人の親族自身は推定相続人ではありませんから、特別受益に該当しません。
事実認定の問題として、真実は推定相続人に対する贈与であるのに名義のみその配偶者としたというような場合は、実質的には相続人に対する贈与があったとみなして特別受益に該当する場合もあります。
3 特別受益財産の範囲
(a) 婚資
婚資とは、持参金や支度金など婚姻(養子縁組)のために被相続人から支出してもらった費用が典型的なものです。婚資は、原則として特別受益に該当します。
ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。
結納金、挙式費用については、実務上確立した扱いがありませんが、結納金や挙式費用が被相続人または相続人にとってどのような意味を持っていたかは一概に断定することができないという事情によるものです。
挙式費用は、通常は遺産の前渡しとはいえませんから、特別受益に該当しないことが多いと思われます。
(b) 高等教育のための学資
高等教育には、親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれません。現在の教育水準に照らせば、高等学校教育も義務教育に場合に準じて考えることができ、高等教育には含まれないのが通例です。
原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。
このような高等教育のために被相続人の支出した費用又は被相続人から贈与された金額は、原則として特別受益に該当します。
ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合、すなわち扶養の範囲内と認められる場合は該当しません。
(c) 不動産の贈与
子供が独立する際に居住用の宅地を贈与した場合や、農家において農地を子供に贈与した場合等が生計の資本としての贈与の典型的なものです。
不動産はそれ自体高額な財産ですから、不動産の贈与は、生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。
(d) 動産、金銭、社員権、有価証券、金銭債権の贈与
相当額の贈与である場合には、原則として特別受益に該当します。
相当額とは、被相続人の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らして、小遣い、慰労金、礼金の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額であることを意味します。
(e) 借地権の承継
被相続人の生前に、被相続人名義の借地権を、相続人の1人の名義に書き換えることがあります。
この場合は、原則として被相続人から相続人の1人に対する借地権相当額の贈与となります。
名義書換に当たり、その相続人が借地権取得の対価と認められる程度の名義書換料を支払っていたときは、借地権相当額から書換料を差引くことになると思われます。
一方、借家権は、原則として承継、設定とも特別受益の問題は生じません。
(f) 借地権の設定
被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与と同視することができ、特別受益に該当します。
相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益に該当しません。
(g) 遺産を無償で使用できることによる利益
1) 土地の無償使用
遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建て、土地を無償で使用している場合
土地の無償利用の場合、通常、被相続人と建物を建築する相続人との間に使用貸借契約があるものと認められます。したがって、その相続人は、占有権原を有することになり、他方で被相続人の財産はその占有権原の価額、つまり使用借権相当額の減少することとなります。
評価は一概には決定できませんが、通常は、更地価額の1割から3割までの間の範囲で各事情によって決定されているようです。
よって、この場合、使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権相当額(更地価額の1割から3割程度)の特別受益に該当するものと考えられます。ただし、上記の建物において被相続人と同居し、被相続人の面倒を見ていたというような場合、これと土地使用の利益は実質的に対価関係に立つことになるため、特別受益には該当しない、あるいは、持戻免除の黙示の意思表示があるとして、いずれにせよ、特別受益性は否定されると考えられます。
なお、使用借権の贈与のみならず、地代相当額も特別受益に当たるとの主張がなされることがありますが、実務的には、地代相当額については特別受益性を否定するのが一般的です。様々な理由の説明がなされていますが、上記の考え方からすれば、土地を無償使用させていなければ、第三者に賃貸し、賃料収入を得ていたというような特段の事情でもない限り、無償使用によって、遺産の減少が生じたとは評価できないからということになります。
2) 建物の無償使用
遺産である建物に相続人の1人が居住している場合
相続人が被相続人と同居していない場合は、通常は使用貸借契約があるものと認められます。土地の使用借権と異なり、建物の使用借権に経済的価値はなく、よって、建物の使用借権の贈与を観念しても、遺産の減価は生じていないため、特別受益には該当しないことになります
また、土地と同様、賃料相当額が特別受益に該当するかが問題となりますが、同様に、第三者に賃貸し、賃料収入を得ていたというような特段の事情でもない限り、無償使用によって遺産の減少が生じたとは評価できない以上、基本的には特別受益に該当しないと考えますこの場合、使用借権相当額の特別受益となります。
被相続人と相続人の間が同居している場合で、相続人に独立の占有権原がないような場合は、相続人には同居したことにより家賃の支払いを免れた利益はありますが、被相続人の財産は何らの減少もありませんから、特別受益には該当しません。
(h) 生命保険金
生命保険金は、被相続人と保険会社が契約し、被相続人が保険料を支払い、被相続人死亡によって、相続人が受取人として保険金を取得するものです。
保険金を支払うのは保険会社であって被相続人ではないため、保険金は被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産となります。
一方で、被相続人は、その意思により保険金額を定め、保険金受取人を指定し、その原資となる金銭支払を負担することによって保険金請求権を受取人に取得させています。相続人の1人が保険金受取人に指定されている場合、結果的には、相続人が被相続人の死亡をきっかけとして保険金を取得し、保険金相当額の利益を受けることになります。このような実質をみると、保険契約を締結することにより、被相続人の将来の財産として保険金請求権を発生させ、これを受取人に贈与したのと同様の側面もみてとることもできます。
判例上は、生命保険金を原則として特別受益に該当しないと扱っていますが、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされています(最高裁平成16年10月29日判決)。
◎判例 最高裁平成16年10月29日判決
死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当たらないと解するのが相当である。
もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
ちなみに、この判決の保険金の額は、総相続財産の約9.6%であり、最高裁判所は、保険金受取人は保険金を持戻す必要はないと判断しました。
この判決以降に「特段の事情」の有無が争われた裁判例を一部ご紹介します。
(1)保険金額が総相続財産の約99.9% ⇒ 持戻しの対象となる。
※東京高裁決定 平成17年10月27日
(2)保険金額が総相続財産の 約6.1% ⇒ 持戻しの対象とならない。
※大阪家庭裁判所堺支部審判 平成18年3月22日
(3)保険金額が総相続財産の約61.1% ⇒ 持戻しの対象となる。
※名古屋高裁決定 平成18年3月27日
※「特段の事情」の有無は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、各相続人と被相続人との関係や各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
(i) 死亡退職金、遺族扶助料
死亡退職金の法的性質は多様なものがありますが、賃金の後払いという性質を強調すれば特別受益となりますし、遺族の生活保障という性質を強調すれば特別受益とならないことになります。
具体的には、死亡退職金の取得者と相続人の範囲との異同、取得者の定め方及び金額の算定方法などから死亡退職金の趣旨が遺族の生活保障にあると推測されるか否か、死亡退職金の取得について被相続人の意思が入り込む余地があるか否かなどを検討して、特別受益に該当するか否かが決められることになります。
遺族扶助料については、通常は法令等によって遺族の生活保障のため支払われるものですから、特別受益に該当しない場合が多いでしょう。
4 特別受益の評価
(a) 評価の基準時
特別受益財産は、相続開始の時点を基準として評価されます (最判昭51.3.18民集30巻2号111頁)。
相続開始時点の評価で具体的相続分を確定することができ、安定性がありしかも一部分割や遺留分算定も統一的に解することができて便宜であること、寄与分制度とのバランスなどが、その根拠とされています。
(b) 評価の方法
1) 贈与の目的物が受贈者の行為によって滅失したり、その価額の増減があった場合
受贈者の行為によって目的物が滅失したり、目的物の価額が増減した場合には、その目的物が相続開始当時、受贈者の行為の加えられない以前の贈与当時の状態のままで存するものとみなされて、相続開始時の時価で評価されます。
2) 贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失したり、その価額の増減があった場合
贈与の目的物が天災その他の不可抗力によって滅失した場合に、その価額を受贈者の相続分から差し引くのは酷ですから、その者は何も貰わなかったものとして、相続分が計算されます。
また、不可抗力によって目的物の価額が増減した場合には、相続開始時のその物の時価によって評価されます。
3) 特別受益財産の具体的な評価方法
金銭については、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するとされています (最判昭51.3.18民集30巻2号111頁)。
不動産、動産、株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権などは相続開始時の時価評価とする説が一般的です。
ただし、建物や婚資として贈与された家財道具のように、年数の経過により減価するものについては、贈与時の価額を相続開始時の価額に評価換えする場合もあります。
5 特別受益がある場合の相続分の算定方法
(a) 共同相続人中に特別受益者が存在する場合には、次の方法で相続分を算定することになります。
(相続開始時の相続財産価額) + (贈与価額) =みなし相続財産額
なお、遺贈の場合には、遺贈財産の価額は相続財産の価額中に含まれていますから、加算する必要はありません。
(みなし相続財産) × (法定または指定の相続分率) =本来の相続分
(本来の相続分) - (贈与または遺贈価額) =具体的相続分
(b) 具体例
1) 超過特別受益者がいない場合の相続分の算定方法
計算例
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。
この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。
妻B : (5,000+1,000)×1/2-600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2-1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円
※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けることができません。
この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を 返す必要はありません(判例・通説)。
2) 超過特別受益者がいる場合の相続分の算定方法
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは200万円の遺贈を、Cは住宅資金として2,500万円の贈与を受けていた。
この場合のBCDの具体的相続額を上記のとおり計算すると次のとおりになってしまいます。
妻B : (5,000+2,500)×1/2-2,000=1,750万円(ほか2,000万円の遺贈)
長男C: (5,000+2,500)×1/2×1/2-2,500=-625万円
二男D: (5,000+2,500)×1/2×1/2=1,875万円
このような贈与をたくさんもらっている人がいる事例だと、上記の方法で算定すると具体的相続分がマイナスとなってしまう人が出てきます。
そして、この場合にはマイナスとなった人は、マイナス分を戻す必要がないとされています。
となると、そのマイナス分を誰がどのように負担するのかという問題が生じます。
この場合の計算方法については、実務上の定説はありませんが、以下のように計算する審判例が多く見受けられます。
具体的相続分基準説
=不足分を特別受益者以外の共同相続人の具体的相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。
本来的相続分基準説
=不足分を特別受益者以外の共同相続人の法定相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。
6 持戻免除の意思表示
(a) 特別受益の持戻しは被相続人の意思を推測し、相続人間の公平をはかるものといえます。
そのため、被相続人が自らの意思で持戻しを免除する場合には、遺留分の規定に反しない限り、持戻しはなされないことになります。
(b) 意思表示の方法
1) 贈与に関する持戻免除の意思表示
贈与に関する持戻免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。
贈与と同時になされることをも必要とせず、生前行為によっても、遺言によっても差し支えありません。
2) 遺贈に関する持戻免除の意思表示
遺贈に関する持戻免除の意思表示は、遺贈が遺言によってなされる以上、遺言によらなければなりません。
(c) 黙示の意思表示
現実には持戻しについて明示の意思表示のある場合は少なく、黙示の意思表示が認められるかどうかが問題となるケースがあります。
持戻しを免除すると、特別受益者は、特別受益財産の価額相当分を相続分より多く取得することになるため、黙示の意思表示が認められるのは、そのような利益を取得する合理的な事情がある場合ということになります。
具体的には、次のような場合が考えられます。
1) 相続人による家業の承継
2) 寄与相続人に対しその寄与に報いるために贈与等がなされた場合
3) 相続人側に相続分以上の財産を必要とするような特別の事情がある場合
例えば、身体的、精神的障害があるために経済的に恵まれない相続人に対し、将来の扶養の意味も含め贈与等がなされた場合などがこれに該当します。
また、各相続人に同程度の贈与をした場合は、持戻しをしないのが被相続人の意思にも合致し、相続人の公平にもかなうことになります。
|
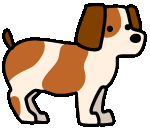 遺産分割調停を乗り切ろう
遺産分割調停を乗り切ろう
